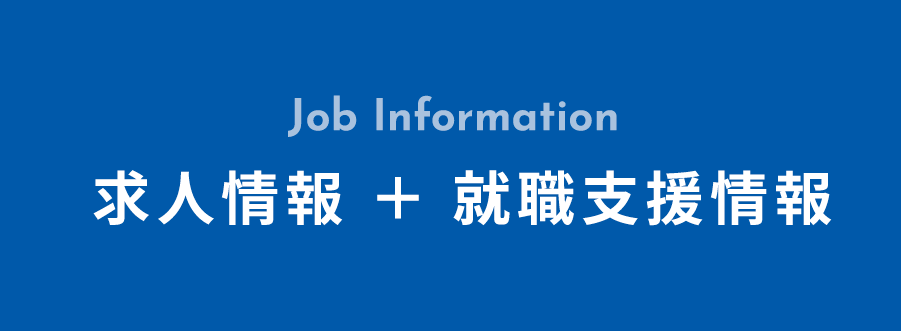文化財(名称):東根の大ケヤキ
種別:特別天然記念物
員数:
(指定):国指定特別天然記念物
指定年月日:昭和32(1957)年9月11日
(所在地):東根市本丸南1の1の1(東根市立東根小学校昇降口前)
(所有者):東根市
(来歴):伝承では、正平年間初期(1346~56)、小田嶋長義築城の時植栽したという。『正保城絵図』(正保2(1645)年)への記載はなく、天保3(1832)年の町屋絵図には、「父槻(ヂヂヅキ)母槻(ババヅキ)」として記載されている。安政年間初期(1854~57)につくられた『松前藩東根陣屋絵図』(本丸周辺)には、25本の大樹が描かれ、そのうちの2本が父親と母槻である。明治15(1882)年、父親が枯れ、同18(1885)年に伐採され、旧家の門やその扉に転用された。大正15(1926)年10月、国の天然記念物に指定された。昭和32(1957)年9月、国指定特別天然記念物となる。
(所見)・(特色):主幹は、地上5.5mの高さでふた股に分かれ、相生の形を成すも相生ではない。目通り(地上1.3m)で16.48m(平成6年9月東根百草会計測)、最大直径5.0mを計る。樹幹に空洞がなければ世界一である。
平成元年(1988)年5月に発表された『日本欅見立番付』には、“東の横綱”に位置付けられ、文字通り日本一の大ケヤキと評された。また、平成6年9月、我が国の樹木医第一号・山野忠彦は、大ケヤキをなめ廻しながら1周し、「こんな立派な巨樹を初めて見た。わが国最大の巨樹だ。もしかすると、屋久島の縄文杉より古い。8500年から8800年の樹齢はある。」と話された。
昭和46年7月から東根小学校の解体が始まる。同50年3月現校舎完成する。そのとき、大ケヤキ周辺に盛土がなされ、最大で1.2m高くなる。そのためか、昭和60年頃から樹勢が衰え出し、同63年には落葉がはなはだしく、消防車で放水を1週間くりかえし、ようやくにして樹勢を取り戻した。
また、平成12年にも落葉があり、龍興寺沼公園造成で沼の水を約2年間抜いたことが原因とされた。
「羽央文化」とは:普光寺梵鐘銘文「小田嶋荘、羽州中央、東根到境、白津之郷……」の「羽州中央」から略称引用